atama plus株式会社
atama plus 株式会社
東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル3F
Sumitomo Fudosan Azabu-juban Bldg. 3F,
1-4-1, Mita, Minato-ku, Tokyo, Japan
Mission
教育に、人に、社会に、
次の可能性を。
教育を新しくすること。
それは、社会のまんなかを新しくすること。
私たちは学びのあり方を進化させます。
学習を一人ひとり最適化し、
「基礎学力」を最短で身につける。
そのぶん増える時間で、
「社会でいきる力」を伸ばす。
それが私たちの目指すもの。
自分の人生を生きる人を増やし、
これからの社会をつくっていきます。
Principle
Wow students.
生徒が熱狂する学びを。
勉強をワクワクするもの、
自分からやりたいものに変え、
生徒一人ひとりの可能性を広げる。
私たちのあらゆる行動は、
ただ、そのためにあります。
Values
Take part.
未来を、一人ひとりが。
私たちは、一人ひとりがMissionのオーナーです。自らの「今日」と、全体で向かう「明日」を結びつけ、自らの仕事でMissionを前へ進めます。

Think beyond.
本質を、たえまなく。
イノベーションは、こつこつと。これまでの「当たり前」にとらわれず、本質を追いつづけ、変化を積み重ねて社会を新しくします。

Speak up.
話すを、力に。
話し合う、磨き合う。意見の違いを「力」に変え、Missionを実現していく風通しのよさと、リスペクトにあふれた場を仲間とつくります。

Run together.
いち早く、共に。
ひとつの大きなチームとして。たがいを信じ、変化に応じ、次々とスピーディーに新たな価値を生み出します。
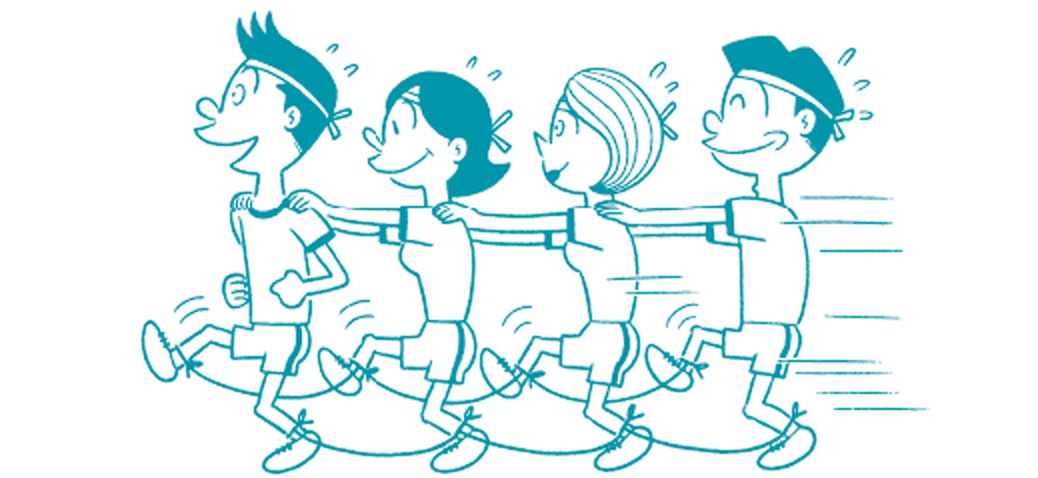
Love fun.
それ、楽しんじゃおう。
社会を変える。それは、困難で当然。チャレンジするからこそ出会えるあらゆる状況を楽しみ、日々笑い合って仕事します。

atama+ culture code
私たちのカルチャーコード
Mission、Principle、Valuesについて
まとめたCulture codeは、
私たちを、私たちたらしめるもの。
何を信じ、何をよいと感じ、
何をリスペクトするか。
atama plusのカルチャーが
記されています。
「全員がCulture codeについて
同じ認識をもち、行動に表れている状態」
であれば
細かなルールなどなくとも、
個々の判断・行動が
常にひとつの大きな方向を向いていく。
Mission実現を加速させることができる。
私たちはそう考えています。
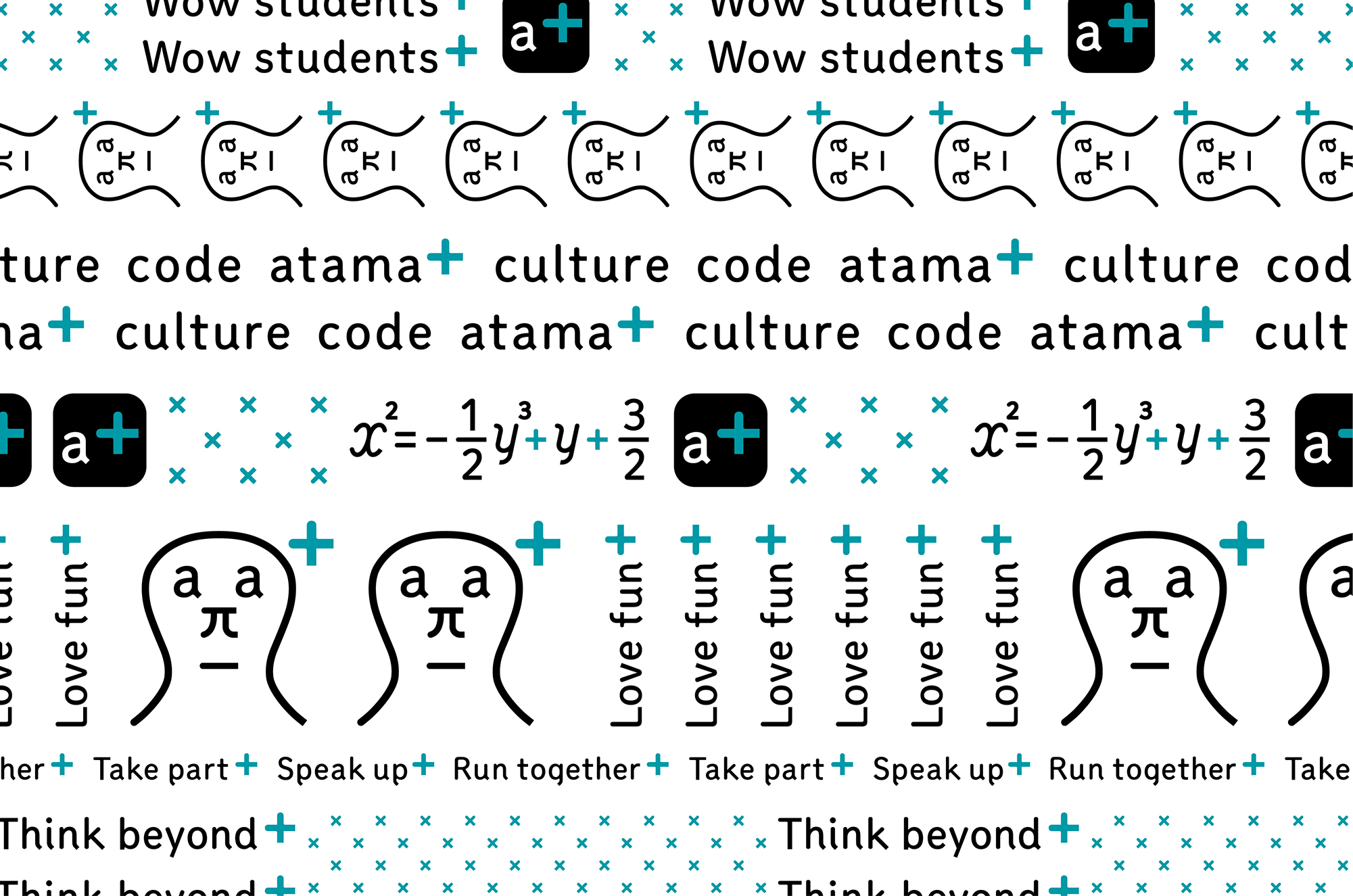 atama+ culture code(PDF版)
atama+ culture code(PDF版)
Message
+Innovation
「社会でいきる力」が変化しています。
教育はどうでしょう?
社会が大きく動いています。これからの子どもたちが生きていく上で求められる力も、今のオトナ世代とは変わってきています。そんな中、教育はどう変わっていくべきでしょうか。私たちは、テクノロジーで基礎学力の習得にかかる時間を半減させ、そのぶん、「社会でいきる力」を養う時間を増やす。そんな明日をつくっていきます。
たとえば自動車や通信。明治以来の150年であらゆるものが大きく変わりました。しかし教育の場を見ると、黒板を背にした一人の先生の話を何十人もの生徒が黙々と聞く、150年前と同じ風景が今日も広がっています。私たちは、それを変えます。教育に進化を+する。未来を+する。私たちはatama+です。
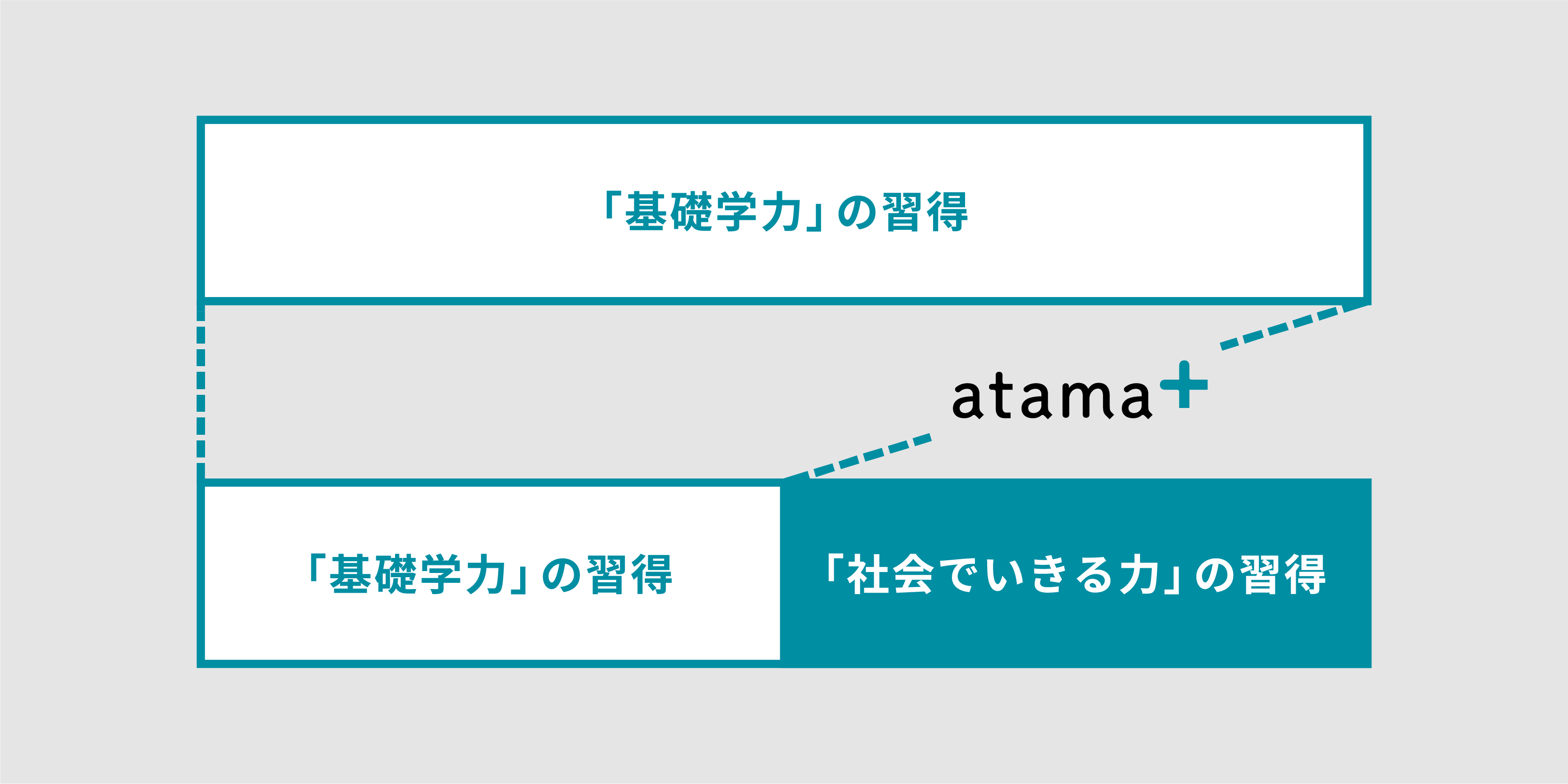
従来の勉強時間を減らし、成長時間を増やす